第七話 黄金の雷(2)
早くも翌日には、まもなくスペイン軍が進軍してくるであろう、このトゥパク・アマルの本拠地たるトゥンガスカの集落の住民たちへ、避難勧告が発令された。
トゥパク・アマルの指揮のもと、インカ軍の専門兵や義勇兵たちに擁護されながら、非戦闘員である当地の貴族や村民たちの避難が大々的に開始された。
特に、高齢者や、病人、子どもたちの避難は、手厚く庇護される。
恐らく、避難をした人々の中には、アンドレスの母フェリパ夫人やコイユールの年老いた祖母も、含まれていたことであろう。
そして、それと併行して、戦略に基づいた、堅固且つ長大な塹壕の建築が着工された。
当然ながら、これまでの戦利品としてスペイン側から奪取した大砲も、要所に設置されていく。
また、その設置作業と共に、クスコ戦の時とは異なり、此度の総決戦ではインカ兵たち自らが大砲を操作できるよう、トゥパク・アマルは本格的な砲撃訓練も開始した。
何しろ、侵略者によって、数百年に渡り、火器を持つどころか、その製造過程を見ることさえ禁じられてきたインカの民は、大砲はもちろん、銃器さえ、まともに扱う方法など知りはしなかった。
反乱幕開け以来、インカ軍の兵たちは、奪取した銃を見よう見真似で扱ってはきたが、それら銃器は兎も角としても、大砲ともなると、その構造や操作を知らなければ、まともに扱うことなど不可能である。
それ故に、かのクスコ戦では、インカ軍の砲撃は、結局、その操作を知る、捕虜とされた元スペイン軍の兵たちに頼らざるを得なかった。
その結果、クスコ戦では、インカ兵の監視の目をかすめ、スペイン人捕虜たちは、敢えてスペイン兵のいないところに砲弾を打ち込むといった裏切り行為を度々行ったのである。
トゥパク・アマルはそれらの事実を苦々しく思うと共に、その時の自戒を込めて、二度と同じ轍(てつ)は踏むまいと決めていた。
此度の決戦では、そのような無駄な砲撃は決してあってはならぬこと!!
この期に及んでは、スペイン人捕虜たちを脅してでも、それら火器の操作を聞き質(ただ)し、インカ兵たち自身で大砲の操作を行えるようにならねばならない。
そして、今や、トゥパク・アマルは実際にそれを行った。
一方、その頃、スペイン軍はインカ軍の奇襲を警戒し、敢えて幾つかの部隊に別れ、トゥパク・アマルが本陣を敷く、このトゥンガスカ目指して着実に進軍を続けていた。
彼らの各部隊は、インカ側に目立たぬよう、少しずつ時をずらしてスペイン軍の本拠地クスコを出立し、ビルカマユ川の西岸に向かって高原の悪路を進んでいた。
だが、その静動とて、刻一刻、トゥパク・アマルが放った無数の斥候たちによって、彼のいるインカ軍本陣に伝えられてくる。
今も、トゥパク・アマルは、斥候たちの報告に、厳しい表情でじっと耳を傾けていた。
「それでは、バリェ将軍の軍は、褐色兵とは行動を別にしているのだな」
彼の目が、鷲のように鋭利に光る。
斥候は、平伏しながら応えた。
「はい、トゥパク・アマル様!
スペイン軍は部隊を分散させながら、当地に向かっております。
褐色兵は部隊の増強のため、まだクスコの地を発ってはおらぬ模様です。
トゥパク・アマル様の予測通り、全軍の先陣を切るのは、スペイン軍総司令官バリェ将軍の軍勢にございます!!」
トゥパク・アマルは、深く頷く。
そして、「ご苦労であった。引き続き、監視を続けてくれ」と誠意を込めて労をねぎらうと、新たに斥候数名を呼び寄せて、バリェが進軍中の進路や陣を張る地の周辺地形、及び敵情をつぶさに偵察するよう更なる指令を出す。

それと共に、すぐさま側近たちを集結させ、進軍中のバリェに奇襲をかけるべく戦略会議を開いた。
此度の敵襲の目的は、バリェを討ち取ることではなく――もちろん、討ち取れればそれにこしたことはあるまいが、そこまで敵将軍を甘くは見ていない上、総決戦に備えて自軍の消耗も最小限に留めねばならぬ故に――むしろ時間を稼ぐこと、及び、敵将軍の部隊に打撃を与えることで、スペイン側の出鼻をくじき、その士気を貶めることである。
トゥパク・アマルは、その目的を側近たち、すなわち、各連隊長たちに説明した後、それに見合う戦略を練り上げていく。
なお、バリェ将軍の部隊を攻撃すれば、インカ軍討伐の最高責任者アレッチェによって、あのフィゲロア率いる褐色兵が即座に戦地に差し向けられるのは必定であった。
当然ながら、インカ族の傭兵である彼ら褐色兵を決して刃(やいば)にはかけぬとの、当初からの方針は、今に至っても厳然として一貫していることである。
その決意は、今まで同様、この後も、決して変わるものではない。
従って、バリェに奇襲をかけた後、褐色兵が現われるまでには、完全に撤退するための退路を確保しておくことも重要である。
つまりは、これから臨む山岳地帯でのバリェとの戦いは、このトゥンガスカの本陣での総決戦に備える戦闘準備を完成させるまでの、言わば、時間稼ぎの「偽装攻撃」とも言い得る種類のものであった。
かくして、トゥパク・アマル及び参謀オルティゴーサを中心に、バリェを襲撃するための一つの計略が練られていった。
トゥパク・アマルは斥候を幾度も放ち、繰り返し、つぶさに敵情と周辺地形を調べ上げた。
その後、かつて雪舞う決戦のあった極寒の険しい山岳の地、サンガララから10キロほど離れた場所にある湿地帯に、此度のバリェとの決戦の場を定めた。
このトゥンガスカのインカ軍本陣に進軍する際、バリェ将軍の部隊が必ず通るはずの場所である。
トゥパク・アマルは、トゥンガスカ周辺に住まう民の避難及び塹壕建築を一任されたフランシスコ及びベルムデスの連隊を本陣に残し、参謀オルティゴーサ、従弟ディエゴ、重臣ビルカパサの精鋭の連隊を引き連れて、敵将バリェよりも一足速く、決戦の地と定めた高原の湿地帯に向かった。
なお、トゥパク・アマルと此度の行動を共にする軍勢は、全体で約二万という、むしろ比較的小規模の、騎兵を中心とした専門兵で構成されていた。
敵軍を討つというよりも、奇襲をかけるに有利であり、且つまた、褐色兵の到来に合わせて、俊敏に兵を引くのに容易である必要があったためである。
もちろん、補給の困難な、険しい自然の要害に陣を構えるために、あまり多くの兵の食糧や水を賄(まかな)いきれぬという、現実的な事情もあった。
トゥパク・アマルらは現地入りをすると、敵将バリェ軍が多数保有する軽騎兵の動きを封じるべく、早速、無数の塹壕を掘りはじめた。
時期は、3月末。
南半球の当地は、秋が徐々に深まる季節。
且つまた、このインカの地は、雨季である。
塹壕を掘り、野営場を設置する指示をくだしながら、トゥパク・アマルは、昼にもかかわらず薄暗い灰色の空を見上げた。
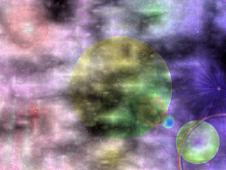
巨大な黒い影のようなコンドルが滑空する曇天は、いつ雨を降らせるかわからぬ色をしている。
天空を見据えるトゥパク・アマルの精悍な横顔を縁取る漆黒の長髪が、下方から吹き上げる疾風によって、乱れながら高く舞い上がった。
雨は、敵が頼る火器の効力を鈍らせる。
火器を使えねば、騎兵と歩兵による肉迫戦になるであろう。
そうなれば、なおのこと、自然の地形と人工的な塹壕の利用価値は重みを増す。
此度の決戦は、「攻め」に出るが、それも、「守備」を徹底させてこそ為し得ることである。
インカ軍が陣を張った高台の上から、トゥパク・アマルは、改めて周囲の厳しい自然環境を見渡した。
この辺りは、ただでさえ険しく厳しいアンデスの地においても、特に、過酷な地勢と気候が支配する場所。
本来は人の拠るところではなく、インカの神々のみが、厳然と、静かに、息づく地である。
トゥパク・アマルは、さらに、視線を移動させていく。
高原の悪路を挟み込むようにして、人を寄せ付けぬ険しい山脈の崖が切り立っている。
しかも、それら狭い悪路の左右前後には、広く深い底無し沼が点在しており、それらの沼は、この土地に暗いものの足を、容易に絡めとリ、沈めゆく。
トゥパク・アマルは、それら広大な底無し沼の一つを山麓に備えた崖上の平原に、インカ軍の陣を張った。
底無し沼は自然の要害となり、塹壕は人工の要害となる。
また、その自然の砦の地は、高度がひときわ高く、この地域全域を容易に監視することができた。
さらに、陣営を敷いたその平原の背後は、切り立った山脈でありながら、その一角は開けており、反対側の山麓に降下することができる、なだらかな自然道になっている。
しかも、眼下の敵からは、その地形は見えない角度になっていた。
トゥパク・アマルが慎重に慎重を重ね、当地を決戦の場と定め、また、陣を張った最大の決め手となったのは、まさしく、その地形、つまりは、退路を確保できるということであったのだ。
かくして、インカ軍が陣を構えて二日後、バリェ将軍率いる精鋭のスペイン軍が当地の悪路にその姿を現した。
突如として眼前の高所に展開するインカ軍の軍勢に、幾多の戦歴を誇る獅子王のごとくのバリェ将軍も、ギョッと目を見張った。
見上げれば、それは遥かに離れた遠方からではあったが、その陣営のひときわ高い見張り台の傍で、あのトゥパク・アマルらしきインディオが、漆黒の翼のごとくの黒マントを翻し、己の方に挑戦的な睨みを利かせているのが見えるような気さえする。
否、目をこらせば、それは明らかに、そのまま、その態度をしたトゥパク・アマル本人ではないか!!
バリェは、瞬間、その鋭い目元を引きつらせたが、すぐに堂々たる険しい眼(まなこ)に戻って、そちらを激しく睨み返す。
(トゥパク・アマル、何故、当地にいる?!
トゥンガスカの本陣に戻る途上か?!
あるいは、敢えて、この自分との決戦を挑んでのことか…――?!)
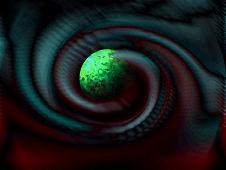
バリェには、にわかにはトゥパク・アマルの意図を図りかねたが、しかし、ここで出会った以上は、決戦あるのみ、である。
実際、当地で決着をつけられれば、全く、それにこしたことはない。
しかも、ざっと目視の範囲では、トゥパク・アマルの軍勢の規模は、さしたる大きさではないように見える。
こうした敵襲に備え、敢えて兵を複数の部隊に分散させて進軍してきた、その己の軍勢よりも、さらに、小規模の軍勢ではあるまいか。
その上、さすがにスペイン軍の総司令官であり、且つ、将軍である己の軍勢は、ひときわ多量の火器、すなわち、大規模な大砲や大量の銃器を装備していた。
バリェは前方のトゥパク・アマルの陣営に睨みを効かせながら、隆々たる筋肉の塊のような厳(いか)つい腕をガッシリと組んだ。
この状況ならば、インカ軍を打ち破るのも、そう難儀ではないのでは…――?!
しかし、戦(いくさ)慣れしたバリェは、事がそう容易ではなさそうであることを、ほどなく察することになる。
バリェは、己の補佐官である腹心のアビレス大佐に、すぐさま敵情の視察に向かわせた。
敵陣を遠目から視察しただけでも、やはり経験豊かなアビレス大佐は、インカ軍が難攻不落の自然の要害に拠っていることを見て取った。
視察から戻ったアビレス大佐は、ひどく苦々しい表情で、バリェ将軍に報告する。
「敵が陣取った山麓には、底無し沼が無数に点在する湿地帯が広がっており、ただでさえ、ひどく攻め難い場所でございます。
その上、あの者どもは、無数の塹壕を掘っており、軽騎兵が攻め入るのは非常に困難でありましょう」
バリェは険しい表情で報告を聞いていたが、その報告にあきたらず、己自身の足で、自ら敵情の視察に向かった。
しかしながら、全くアビレスの言う通り、これを攻略するのは至難という結論に達せざるを得なかった。
スペイン側も、周囲の地勢を可能な限り慎重に吟味した後、悪路を挟んだ反対側の山麓の崖上に陣を張った。
今、下界の悪路を挟んで、両者は山上で対峙する形勢となっていたが、それでも、インカ軍の方が遥かに高所に陣を張っており、スペイン軍を見下ろす形になっている。
トゥパク・アマルはスペイン軍の動きの始終を高所からじっと見下ろし、今、その表情には、薄っすらと笑みさえ湛えているように見える。
そろそろ日暮れも近い。
曇天に、淡い茜色が射している。
先刻から傍で控えるビルカパサが、トゥパク・アマルの指示をじっと待ち、その足元に跪いている。
「今は、十分に兵を休ませよ。
暫く、このまま、時間を稼ぐ」
トゥパク・アマルの言葉に、ビルカパサは深く恭順の礼を払い、素早く消えた。
身を切るような突風が、吹き過ぎていく。
トゥパク・アマルは、天を振り仰いだ。
そして、インカの神々に呼びかける。
天空の神よ、大地の神よ、インカを守り給え。
そして、決戦のその時には、恵みの雨を…――!!
一方、敵将バリェは、アビレス大佐をはじめ、側近たちを招集し、軍議を開いていた。
インカ軍が地の利を得ていることから、急に攻めるのは賢明ではない、と話し合う。
そして、いっそのこと封鎖作戦に出るのが得策であろう、との結論に達した。
「恐らく、あれほどの自然の要害であれば、逆に封鎖を受ければ、やがて食糧や水が尽きようとも、その補給は困難。
インカ軍の背後も、我らと同じ、前人未踏の巨大な岩壁。
そう容易には、逃げられる心配も無かろう。
ここは、焦って攻めるよりも、持久戦に持ち込み、じっくり着実に、息の根を止めるのが得策」
全く隙の無い厳然とした面差(おもざ)しで語るバリェ将軍のもと、アビレス大佐をはじめ部下たちも同意を示した。
それから1週間、両軍の間では、無言の睨み合いの日々が続いた。
トゥパク・アマルは見張り台の傍で、じっと天空を仰ぐ。
鋭い横顔で、空の色を見る。
灰色の雲はますます厚く立ち込め、日中にもかかわらず、周囲はすっかり薄暗い。
彼は、鼠色のぶ厚い雲を見つめたまま、その目を細めた。
己の本陣トゥンガスカでは、バリェを足止めしているこの期間に、住民の避難と塹壕の造営が進んでいることであろう。
(そろそろ、か…――)
トゥパク・アマルの傍に立つ参謀オルティゴーサも、「雨の臭いがしてきましたな」と、太い声で呟くように言う。
トゥパク・アマルは、ゆっくりと頷いた。
「今宵、天地の神の動きによって、奇襲をかける。
全軍に準備を」
「はっ!!」
オルティゴーサは深く礼をすると、騎兵隊の軍勢の方に、勇壮な足取りで歩み去った。
一方、反対側の崖上に陣取るバリェ将軍率いるスペイン軍は、この数日間のインカ軍の静まり返りように不気味さを抱いていた。
既に、要所に複数の大砲を配備し、銃器を携えた無数の兵たちが、随所に配置されている。
しかも、早々に、総指揮官アレッチェのもとに使者を飛ばし、インカ軍の動きを封じるのに最も有効な、かのフィゲロア率いる「リマの褐色兵」を、援軍として当地に向かわせるよう要請も出していた。
このまま厳重な封鎖を続け、篭城攻めよろしく、インカ軍が自ら息絶えるのを根気強く待つか、あるいは、褐色兵が到着する前にインカ軍が動けば火器で徹底的に応酬し、一方、褐色兵が到着さえすれば、それら同族には手出しをせぬ敵を打ち崩すのはさらに容易。
もちろん、戦歴経験豊かな将軍バリェに「油断」の文字は無い。
が、それでも、いずれにしろ、インカ軍を陥落させるのは時間の問題ではないか、と思われた。
かくして、その日も、表面的には、如何なる動きも無いまま、日が落ちる。
当然ながら、夜間の奇襲に備え、バリェの指示のもと、見張りの兵も厳重に配備されていた。
だが、その日の深夜……。
ついに、インカの神々は、恵みの雨を当地に注ぎはじめる…――!!


